ライソゾーム病に関して(各論)医師向けファブリー病
疾患番号 30
1.概要、欠損酵素など
本症の原因はライソゾーム酵素の一つである、αガラクトシダーゼが欠損することにより、その基質であるグロボトリアオシルセラミドを始めとする糖脂質が血管内皮細胞、平滑筋細胞、神経節細胞などに蓄積する疾患である。本症は1898年に英国の Anderson 博士と独逸の Fabry 博士の両皮膚科医が angiokeratoma corporis を伴う患者を記載したのが初めてである。蓄積物質の証明は1963年に Sweely らによりなされ、欠損酵素の発見は1966年 Brady らにより発見された。
2.遺伝形式
X染色体劣性遺伝形式をとる。
3.分類
四肢痛、低汗症、皮膚の被角血管腫、腎不全、心肥大など典型的なファブリー病の症状を呈する古典型、心臓の症状に限局する心型、腎臓の症状にほぼ限局する腎型の3つがある。X染色体劣性遺伝形式をとるため男性のみに発症すると考えがちであるが、X染色体の不活性化の偏りにより女性も多くの場合男性よりは軽症であるが、様々な症状を呈する。
4.人種差、発症頻度
現在までの報告としてはオーストラリアで1/117,000(Meikleら、1999)、オランダで1/476,000(Poothuisら、1999)がある。発症率に人種差はないとされている。最近、イタリアで新生児期にマススクリーニングを行い、それによると1/3,100出生に酵素欠損があったと報告されている。
5.症状
症状は多岐にわたる。以下の表に示す。
| 皮膚症状 | 被角血管腫、下肢のリンパ浮腫 |
|---|---|
| 循環器症状 | 心筋肥大、弁膜症(特に僧房弁)、不整脈、虚血性心疾患、刺激伝導障害 |
| 眼症状 | 角膜の渦巻き状混濁、結膜の静脈怒張、網脈中心動脈閉塞症 |
| 耳症状 | 耳鳴り、めまい、難聴 |
| 消化器症状 | 腹痛、下痢、虚血性腸炎 |
| 腎症状 | 蛋白尿(初期症状)、腎不全 |
| 神経症状 | 四肢の痛み、低汗症、脳梗塞、頭痛 |
女性患者の場合も表の様な様々な症状を呈する。我々が調査した女性患者の症状を表に示す。
| *我々の検討 (n=36) |
|
| 被角血管腔 | 5.60% |
| 四肢痛 | 50.00% |
| 低汗症 | 16.77% |
| 角膜混濁 | 50.00% |
| 蛋白尿 | 38.90% |
| 腎不全 | 5.60% |
| 左室肥大 | 38.90% |
| 脳血管障害 | 8.30% |
| 上記のいずれか | 86.10% |
| *Kobayashi M. et al. Journal of Inherited metabolic disease, 2008. |
|
6.診断
ヘミ接合の男性の場合、診断は容易である。白血球、血漿、培養皮膚線維芽細胞中のαガラクトシダーゼ活性を測定し、その低下を証明すれば良い。通常、正常の10%以下の活性である。尿中のグロボトリアオシルセラミドを定性、定量することによっても診断可能である。我々の研究班では尿中のαガラクトシダーゼと尿中のグロボトリアオシルセラミドを測定する事による診断法を開発した。問題は女性のヘテロ接合である。酵素活性は正常と重なる症例も多い。尿中のグロボトリアオシルセラミド定性、定量は診断の一助となるが、それだけで診断は出来ない。臨床症状と合わせて診断することになる。最終的には遺伝子診断で行なうが、男性患者の母親だからといって、ヘテロ接合とは限らない(de novo変異がある)。へテロ接合の患者の診断は遺伝子診断なしで家族歴、臨床症状より診断をつける事も多く、これだけでも医療費の認定基準には合致する。
7.治療
- (1)四肢痛に対して
- 四肢痛に対してはカルバマゼピン(製品名 テグレトール)が有効であり第一選択薬である。一般的な非ステロイド系の鎮痛薬は効果がないし、また腎機能にも悪影響があるのであまり使用すべきでない。その他、ジフェニルヒダントイン、アミトリプチリン、ノイロトロピンなどが、効果があるとされている。カルバマゼピンが過敏症などで使用できない患者さんには試みる価値があるが、実際に使用してみると、カルバマゼピンほどの効果はない印象がある。カルバマゼピンの副作用として房室ブロックが知られており2度以上の高度房室ブロックがある場合は禁忌とされている。ファブリー病では刺激伝導系へのグロボドリアオシルセラミドなどの蓄積により房室ブロックが併発する可能性があるため、これを合併している場合は使用に注意を要する。しかしながら、四肢痛は患者さんの QOL, ADL を著しく阻害するため使用せざるおえない場合も多い。ギャバペンチンが欧米では効果があるとされている。本邦で「てんかん」に対してのみ適応がある。
カルバマゼピンの投与量は常用量でかまわない。〈例〉テグレトール細粒、テグレトール錠(100、200mg) 成人 テグレトール錠(200mg)1錠を1日2回 小人 テグレトール細粒 4mg/kg/日、分2ぐらいよりスタートして 10mg/kgまで増量可能。教科書的には 25mg/kgまで可能だが 10mg/kgぐらいで押さえておいた方がいい。 - (2)腎不全に対して
- これは一般的な腎不全の治療と変わるところはい。最近アンギオテンシンII阻害剤を用いることにより腎機能保護に有効であるとの報告があったがエビデンスレベルの高い報告は現在のところない。末期腎不全に至った場合は血液透析、腹膜透析の適応となる。腎移植に関しては、当初は移植腎にグロボトリアオシルセラミドなど再蓄積するなどとして、否定的であったが、その後の報告では肯定的な報告が多く、もしドナーがいる場合は試みる価値があるとされている。ただ家族をドナーとする場合、例え腎機能が正常でも母、姉などヘテロ接合の女性はさけるべきである。
- (3)酵素補充療法
- 本症に対する酵素補充療法は本邦では2004年より導入された。現在、2製剤(製品名ファブラザイムとリプレガル)がある。ファブラザイムは CHO 細胞(ハムスターの卵巣細胞)に人のαガラクトシダーゼ cNDA を導入し大量発現させた後に培養上清より精製したものである。もう一つの製剤であるリプレガルは gene activation という手法にてヒトの培養皮膚線維芽細胞を用いて、内在するαガラクトシダーゼ遺伝子を大量発現させてやはり培養上清より精製したものである。酵素学的に両製剤には差がないとされているが投与用量が異なる。ファブラザイムは 1mg/kg を2週ごとに点滴静注であるが、リプレガルは 0.2mg/kg を2週ごとの点滴静注である。
〈体重が60 kgのヒト〉
①生理的食塩水 500 ml
ファブラザイム 60 mg/4時間で点滴静注(0.25mg/min)副反応がなければ2時間で点滴静注も可(0.5mg/min)。②生理的食塩水 100 ml
リプレガル 10.5 mg/40分で点滴静注 - (4)酵素補充療法の副作用
- 本邦に治験において最も多く認められた有害現象は投与時の悪寒、発熱、鼻汁、発疹などのアレルギー反応である。これらは約半数程度に認められた。大半が軽症であるが、中にはIgEが陽転化してアナフィラキシー症状を呈した例もあり注意を要する。対処方法としては投与速度を遅くしたり 、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、ステロイド剤の前投与(投与開始1時間前)したりすることによりコントロール可能である。女性ではアレルギー反応はきわめてまれである。その他、本剤と関連のあるような副作用は認められていない。使用禁忌は本剤に対してアナフィリラキシーショックの既往のある患者である。また女性ではアレルギー反応はきわめてまれであった。本研究班で行なった調査では男性患者20例中9例にアレルギー症状を認め、最も多かった症状は悪寒、発熱であった(下図)。
(ファブラザイムを使用した症例)
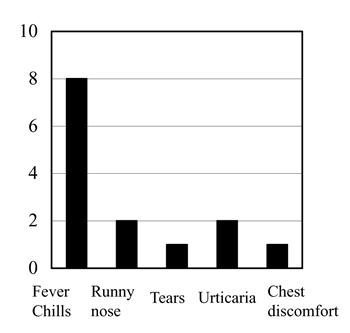
- (5)酵素補充療法のエビデンス
- <ファブラザイム> 第1/2相試験に引き続き第3相試験としてランダム比較試験が行われた(エビデンスレベルIb)。第3相試験のエンドポイントは腎病理の改善度合いであった。腎の毛細血管内皮細胞の蓄積物質の蓄積度をスコアー化して比較したが偽薬群に対して実薬群は有意に改善した。その他血漿グロボトリアオシルセレミドの減少などにも両群間で有意差を認めた。
本邦においてもランダム化比較試験ではなく投与前後の比較試験であるが臨床研究が行われた(IIa)。対象症例は13例であり結果は欧米の第3相試験と同様であった。
第4相試験はファブラザイムが腎イベント(血清クレアチニンがベースラインより33%増加、または末期腎不全)心血管イベント(急性心筋梗塞、不安定狭心症、不整脈、心不全)、脳血管イベント(脳卒中、一過性脳虚血発作)または死亡のリスクをどれくらい減らせるかを実薬群と偽薬群で検討した(エビデンスレベルIb)。結果は実薬群において有意にイベント発症が抑制されていた。以上、ファブラザイムは病理学的所見のみばかりでなく、本症の様々なイベントを予防する意味でも効果があることが確認された。
<リプレガル> 第1/2相試験に引き続き第3相試験が行われた。本臨床試験はランダム化比較試験で、疼痛の改善が主要エンドポイントであった。(エビデンスレベルIb)。疼痛はペインスコアー(BPIスコアー The Brief Pain Inventory short form)を用いて評価を行い、実薬群はプラセボ群に比べより痛みが低下した。
本酵素療法をいつから始めるべきかの明確なガイドラインはない。本症のエクスパートが集まってある種のガイドラインを出している(エビデンスレベルIV)。これによると男性の成人患者は診断後すぐに、女性の患者は一つでも血管障害を示す所見があればとなっている。先にも述べたが女性の場合、アレルギー反応などの副作用を認めることは稀であり比較的安全に治療が可能である。
8.予後、自然歴
予後、自然歴に関しては、Barnton らの報告が有る(J Am Soc Nephrol 13:S139, 2002)。 105例の男性古典型ファブリー病患者での検討である。それらによると、50%の患者さんが43歳までに腎機能障害を呈し、53歳までに末期腎不全となるとしている。また、未治療の場合、腎機能障害発症後、年間 12.2ml/minGFR が低下するとしている。
